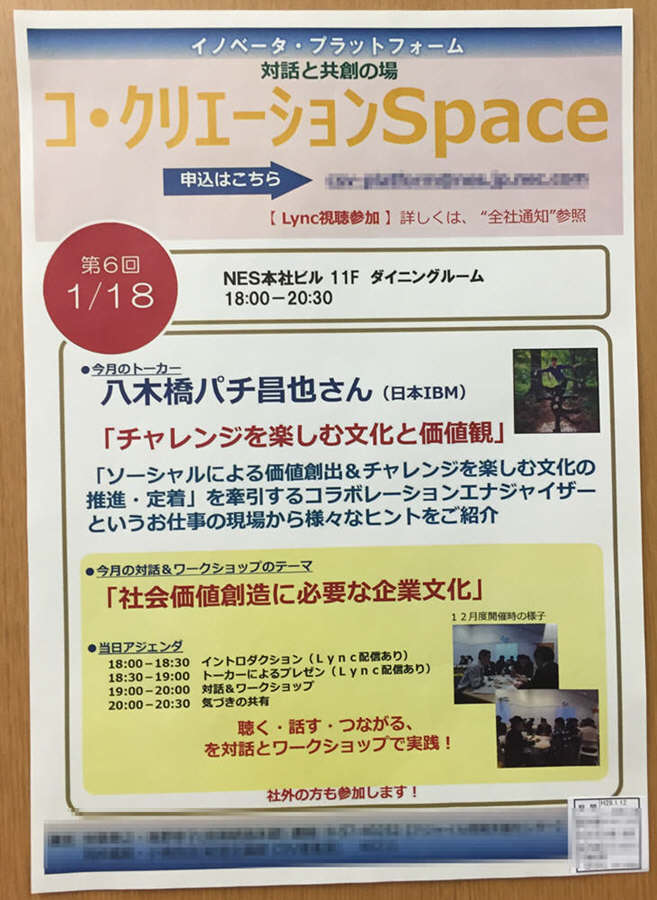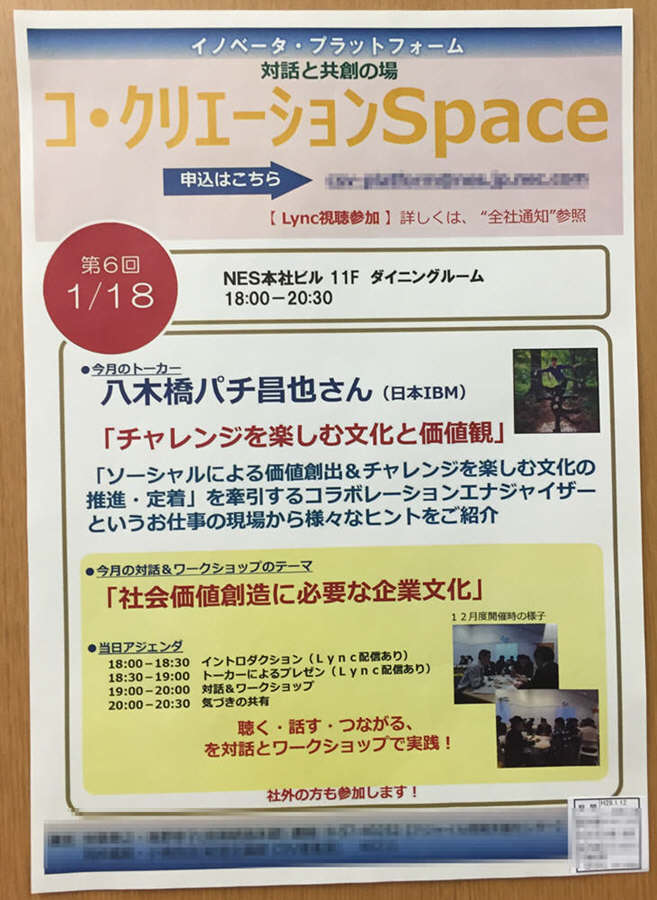
朝から激しい雪が降っていたちょうど一週間前の月曜日、社会価値創造活動を目的としたNECさんの勉強会「コ・クリエーションSpace」にゲスト・スピーカーとして呼んでいただき、『チャレンジを楽しむ文化と価値観』というタイトルで40分ほど講演をさせていただきました。
ときどきこうしたスピーカー役をやらせていただく機会があり、いつもありがたく思っているのですが、今回はとりわけありがたいことがありました。
普段、こうした講演後は会場で質問を受けてQAをしたり、後日アンケートフィードバックとして感想を教えてもらうことが多いのですが、今回は私の話を受けて感じたことをスタート地点とするワークショップに参加させてもらったんです。
話を聞いてどう感じたか、どんな気持ちになったか。
違和感や嫌悪感を感じたのはどんなところか。
他の人の共感ポイントや違和感ポイントを聞いて、そこから何が頭に浮かんだか。
ワークショップを通じてこれらのことを参加者同士で共有し、掘り下げていく共同作業に参加させてもらうことで、普段アンケートなどを通じてもらうフィードバックとはその「深さ」に大きな違いがあることを実感しました。
とりわけ、「違和感や嫌悪感を感じたポイント」は、なかなかスピーカー本人に率直にフィードバックできないという人も少なくないと思うのですが、この日は運営チームのとても丁寧なファシリテーションのおかげで、違和感の根本にある捉え方のズレのようなものに触れられました。
これって、本当に私にとっては一番のご褒美で、最高の「しゃべり甲斐」です!
当日使用したファイルをSlideShareにアップしたので、ご興味があれば見てみてください。
以下、対話の場で私がとても興味深く感じた「チャレンジ」にまつわるいくつか、を書いておきます。
■ 優秀な人や結果を出し続けてきた人ほど、チャレンジできない
参加された方の「とは言えやっぱり失敗したくない」「失敗は内緒にしたい」という話を聞きながら、自分がとってもチャレンジしやすい環境にいることに改めて気がつきました。
「これまでしょっちゅう失敗してきたし」「失敗も積み重ねていけばなんとなく形にはなるものだし」「手にしているものって実際の姿よりも大きく見えるものだし」「そもそもそれが自分にとって本当に失敗かどうかを決められるのは俺だけだし」
こんなふうに考えられるのは、自分がメインストリームを外れ失敗を重ねる生き方をしてきたからだろうと思います。
(とは言え、こんな私でも「楽しもうという気持ち」や「自己効力感」が落ちているときは、チャレンジを躊躇してしまうのですが。)
■ 評価者と批評価者の関係性に流動性があると(ないと)、チャレンジできない
私はこれまで「長年同じ上司と部下の組み合わせ」で「昔からの成績をずっと引きずっている状態」では部下(評価される側)はチャレンジしづらくなるものだと思っていて、それは誰しも同じだと思い込んでいました。
つまり、チャレンジに失敗してしまうと「失敗した部下」という評価が関係性の中にずっと残ってしまうので、それはリスクの取りづらさにつながるだろうなと思っていたんです。
でも、真逆の捕らえ方をする人もいるんですね。
ワークショップの中で「私は違います。一度その人の前で失敗しても挽回するチャンスが先にあることが見えているわけだし、何よりも自分のスタイルや志向性を長年の関係性の中で理解して貰えていると思えなければ、チャレンジできません」と言われる方がいらっしゃいました。
これって私にはメウロコ(目から鱗)でした。
どちらの考えが良いとか悪いとかって話ではないと思いますが、これもどこか前述の「失敗経験の豊富さ」と大いに関係している気がします。
皆さんはどっちのタイプですか?
■ 何が「チェンジ」と「チャレンジ」の目的なのかを見据える
「チェンジ」や「チャレンジ」という言葉は、ときに「これまでを否定された」と相手に感じさせてしまうことがあるようです。場合によっては「これまでの自分自身を否定された」なんて捉えられてしまい、ポジティブなコラボレーションからはどんどんと離れていってしまうことも…なんて話を聞きました。
なるほど、たしかに。
目的が「チェンジという言葉を使うこと」なら話は別ですが、普通はそうじゃなくて、行動や思考をチェンジして結果をチェンジすることが目的ですよね。
それなら、チェンジや変化という言葉にこだわらず、包みこむ力の強い「拡げる」「拡張する」という言葉を使い、無用な争いを避け結果としてチェンジを手にする方を選んだほうが良いんじゃないかということでした。
チャレンジが成功するかしないかって、実はこんなところが決めてだったりするよなって思います。
でもこれ、冷静に話として聞いているとヒャクパー納得なのですが、実際にその場の中にいるとなかなか実行できないものなんですよね…。
他にもいろいろありましたが、長くなってきたので今回はここまでとします。
機会をいただいたコ・クリエーションSpaceの皆さんありがとうございました。

Happy Collaboration!