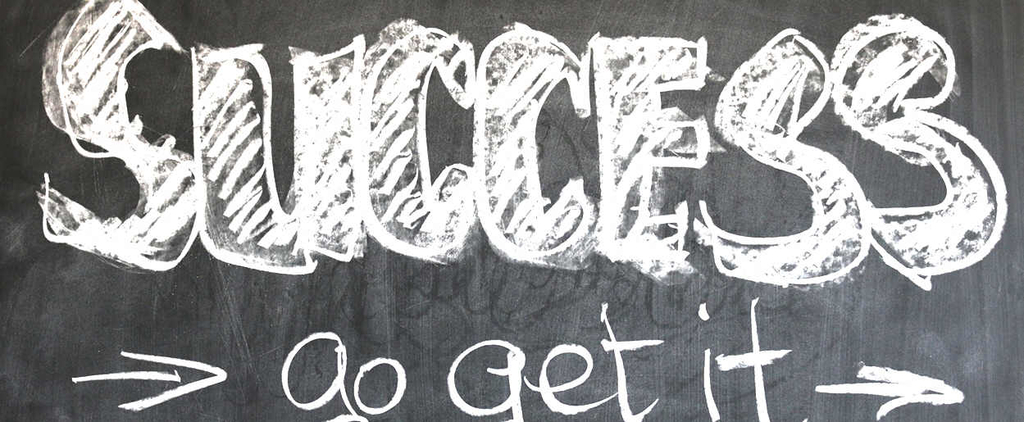オリジナルはこちら(2016/03/14)

ここのところ「社内ソーシャル・ガイドライン」について問い合わせを受けたり、アドバイスを求められたりする機会が再び増えています。
新入社員がやってくる時期というのが関係しているかな? なんて思っていたのですが、「LINEの手軽さを職場に持ち込みたいという若手からの要望が増えているからじゃないですか?」という友だちの言葉にもなるほどと納得しました。
本当なら、まずは社内ソーシャルのガイドラインやポリシーの策定について概要的なことが書かれているウェブページを紹介して見てもらい、その上で個別の相談に…と行きたいところなのですが、実際には検索しても出てくるのは社外で使用するソーシャルメディアに関するものばかり…。
社内ソーシャルに関するガイドラインについては、ほとんどウェブ上には存在していませんよね。
そんな状況なので、まずはこれまで私が相談を受けた際に伝えてきた「社内ソーシャル・ガイドライン/ポリシー」のベースとなる考え方やポイントを7つご紹介します。
なお、ここでは実名制の社内ソーシャルであることを前提としています。
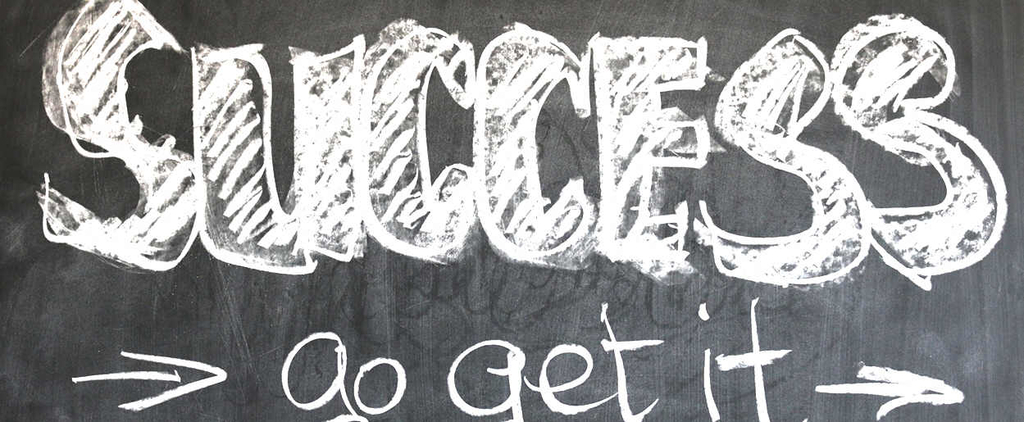
1. まず、会社側の考える「社内ソーシャルを持つ理由と意義、そして社員に期待している行動」を伝える。
そして意見やコメントがウェルカムであることを明確にする。
2. 自身の現在の社内におけるコミュニケーションスタイルを起点とした利用を促す。
「オンラインでは別人格」ではなく、一人の社員としてのインテグリティーを求める(なお、運営側にも同じ意識が求められる)。
3. 「べからず」を細かく挙げていくとどこまでもきりがなく、例外や重箱の隅との戦いを続けざるを得なくなるのでやめる。
基本は「オフラインでの社内行動でNGなものはオンラインでもNG 」。
4. 社内にはまったくソーシャルに触れたことがない社員もいることをくれぐれも忘れない。
推奨される使い方をいくつかの例と共に具体的に明示してあげると初心者もイメージしやすい(典型的、あるいは運営チームの考える「グレーに近いNG」を 例示するのもイメージしてもらいやすい)。
5. オンラインの特性(顔や声色が分からないため、発信する側が独断的になりがちだったり、受けとる側が勘違いしやすかったり)を意識するよう呼びかける。
特に、ソーシャルやインターネットを使い慣れている社員こそ「悪い部分」も持ち込みやすいので、ソーシャルの概念に不慣れな社員が多いことへの配慮を持った「先輩としての行動」を求める。
6. 既存の(ソーシャルからは離れた)社員向けの行動規範やガイドが存在するのなら、それを土台として考える。
あるいは、これを機にオンラインに限定しない社員向けのコミュニケーション全般の網羅的なガイド作成検討も考慮に入れる。
7. ガイドライン/ポリシーは1部門だけで完成させず、関与が高いと思われる部門と協業して作成する(ただし、あくまでも「べからず集」にならないように注意する)。
完成後はさまざまな方法で広く社員に周知する(使われないガイドラインは無駄)。また、定期的に見直し/改定を実施する。

さて、それではIBMではどんな社内ソーシャル・ガイドラインを使用しているかというと…実は、社内向けのソーシャル・ガイドラインは存在していないのです。
びっくりしましたか? ただ、実際には「社内向け」や「ソーシャル専用」と切り離していないだけで、以下の3つのガイドラインで上記の「7つのポイント」をカバーしています。
- ビジネス・コンダクト・ガイドライン
- ソーシャル・コンピューティング・ガイドライン
- セキュア・コンピューティング・ガイドライン
また、オンライン学習用の教材が毎年更新されており、受講とテスト合格が全社員に義務付けられています。
社内ソーシャルを「全社員の業務遂行を支える基礎プラットフォーム」と捉えるのであれば、こうした強制的な進め方も必要となってきます。
最後に、これまでに社内向けガイドライン/ポリシーに関連するブログ記事をいくつか書いているので、そちらも紹介しておきます。
Happy Collaboration!